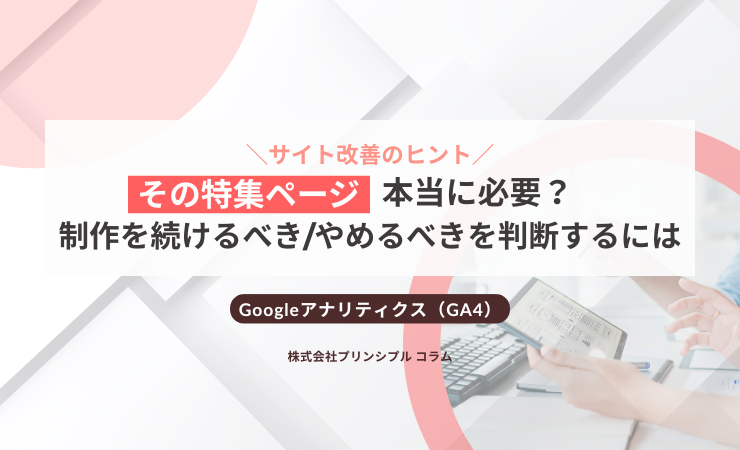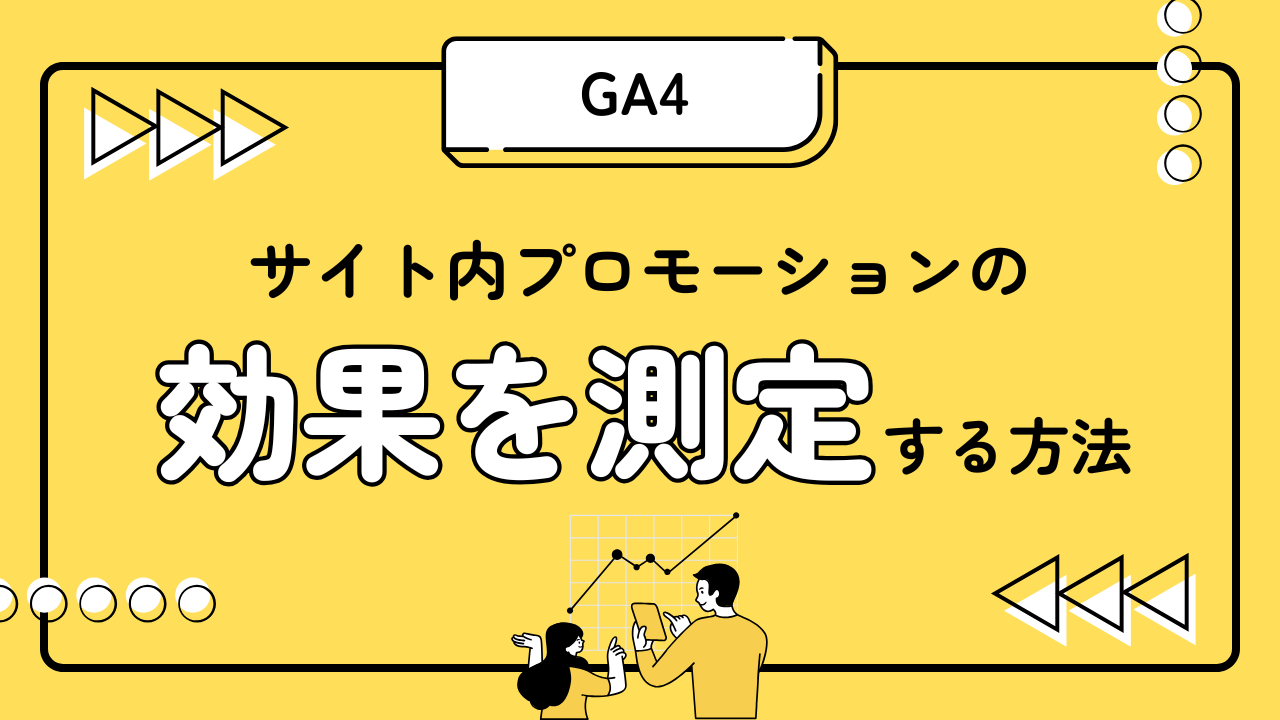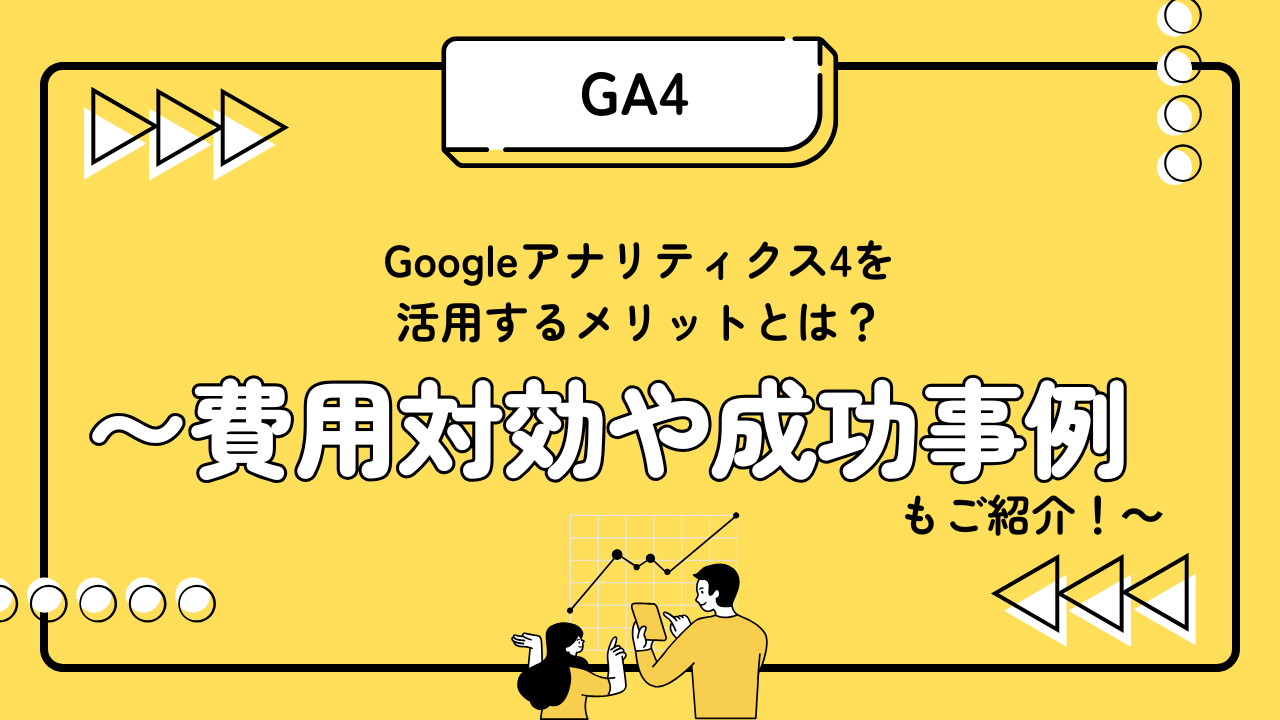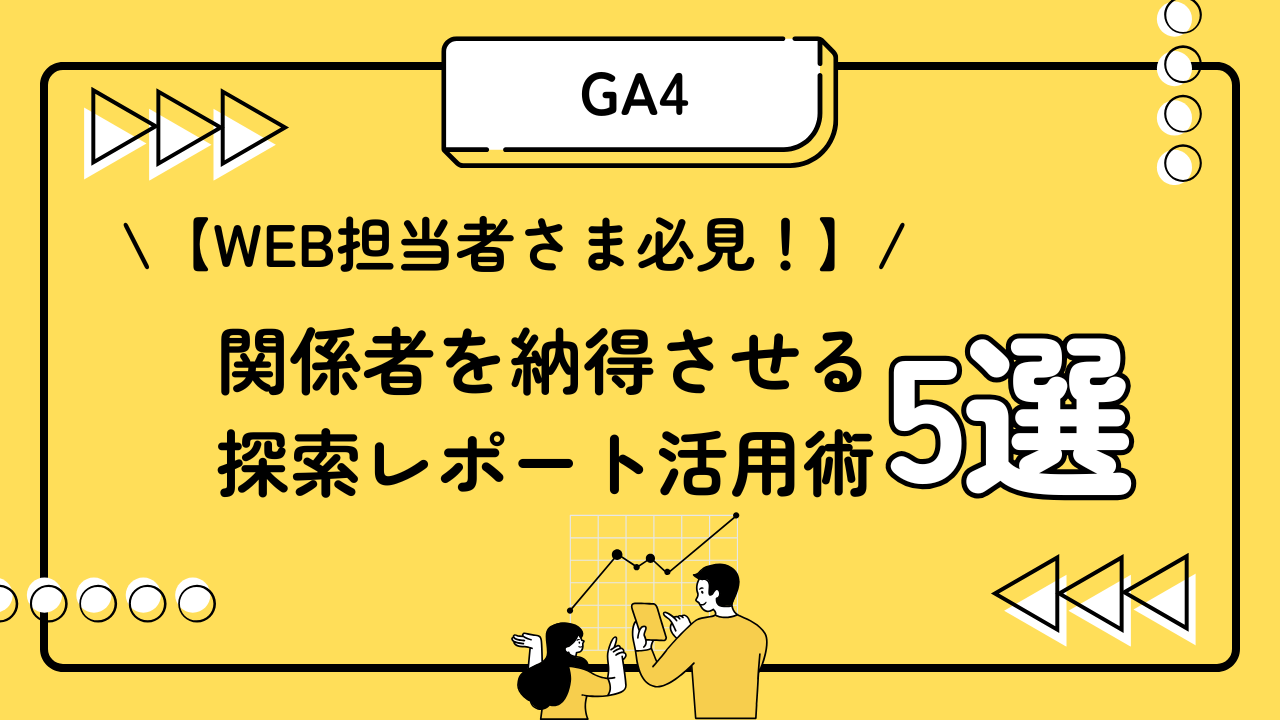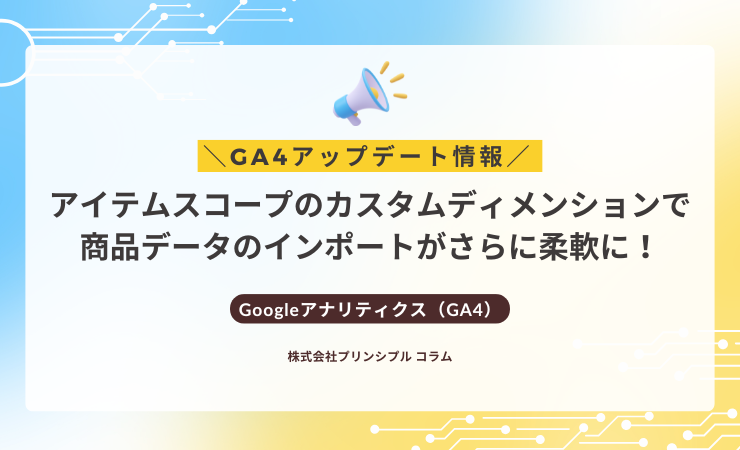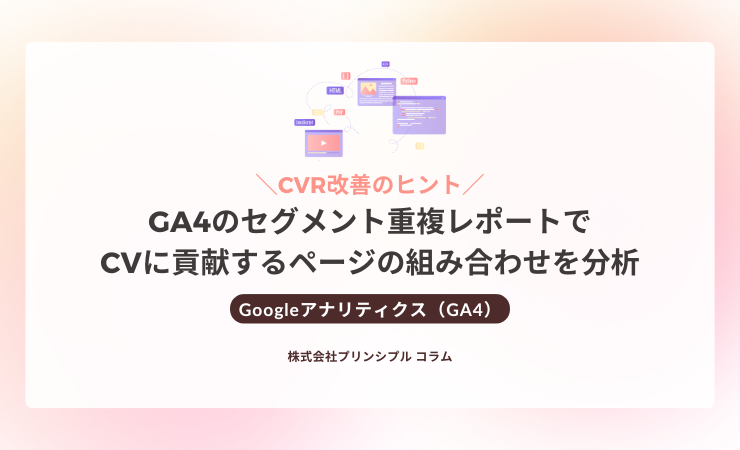特集ページ。それはウェブサイトの華であり、同時にウェブ担当者の頭痛の種でもあります。
集客の看板であり、サイトの資産でもある一方で、リンク切れ多発地帯でもあり、時間とコストをいくらでも消化してしまう存在。しかも、その割にいまいち成果が見えにくかったりします。
また近年は、商品一覧など動的ページの精度・速度向上、ブログ記事やホワイトペーパー等の台頭も充実。その結果、特集ページを制作しないサイトも増えてきた印象です。
本記事では、「もしかして特集ページ作りってもう古い?」「どうやって効果検証したらいいの?」「より有効な施策って何かある?」という観点から考えを整理し、
「特集ページって本当に必要?」
この問いに向き合ってみたいと思います。
王道のウェブマーケティング施策だった「特集ページ」
執筆者である私はいまウェブ解析コンサルタントを務めていますが、以前は事業会社におけるECサイトやウェブメディアを運営する、ウェブマーケターの1人でした。
2010年代はほとんどの時間を「どうやったら自社サイトの売り上げが伸びるか」というミッションに費やし、特集ページも多数制作してきました。当時は、特集ページは多くのサイト、特にECサイトにおいてはほぼ必ず制作されていた、ウェブマーケティングの王道施策だったように思います。
まず前提として、ここでは特集ページの定義を下記のように定めたいと思います。
- 特集ページ = 企画軸でユーザー導線を設計する静的な「ハブ型コンテンツ」
- 商品やテーマを軸に独自構成で設計され、集客・回遊・CV促進を担う企画型ページ
企画軸およびタイトル例
- 季節軸:「夏休み旅行特集」「バレンタインプレゼント特集」「春期講習 早割キャンペーン」
- 商品軸:「新機能○○搭載エアコン 最新モデル特集」
- ニーズ軸:「汗かきさん注目!通気性抜群ウェア」「シーン×相手の年代別でランキング!人気プレゼントTOP3」
特集ページに期待する役割
特集ページはなぜ必要とされてきたのでしょうか。「期待されてきた役割」という軸で整理すると、以下のようなものがあります。
- SEO施策としての流入獲得:
ターゲットキーワードに即したページ構成・内容により、Google高評価および自然検索流入を獲得する - 広告・SNS・メルマガ等 集客媒体におけるクリック率向上:
魅力的な企画・タイトル・ビジュアルで、サイトへのリンククリックを集める - ランディングページとして直帰防止・回遊促進:
特集から閲覧開始したユーザーを引き留め、回遊・購入へつなげる - 離脱防止・回遊促進:
ニーズが顕在化していないユーザーを引き留め、回遊・購入へつなげる - 特定商品のプロモーション:
ユーザーに商品を提案し、訴求によって購入につなげる - リピートユーザーとの関係維持向上:
充実したコンテンツを定期的にリリースし、リピートユーザーの訪問動機を形成する - ブランドやストーリーの訴求:
「世界観」や「質の高さ」など、数値化できない価値を丁寧に訴求し、ファン醸成や購入動機形成につなげる
特集ページの必要性が低下している3つの例
上記のような役割を期待される特集ページですが、近年の流れや技術の発達により、より効果的な代替手段が増えています。以下では、特に特集ページの必要性が低下しやすい3つの例を紹介します。
1. 検索性・回遊性がCVRに直結するサイト
商品点数が多く、ユーザーが自ら検索・比較・絞り込みをするECサイトなどがあてはまります。こうしたサイトでは、特集ページよりも検索結果ページやカテゴリーページなど、動的に生成されるページの最適化に力を入れたほうがROIは高くなりやすいでしょう。
以前はこういった動的ページは読み込みが遅かったり、検索項目が限られたりしていましたが、近年ではUX改善やシステムの高度化によって、こういった課題を克服したサイトも多い印象です。
2. SEOや情報系コンテンツの比重が増している場合
かつては、特集ページがSEO施策のランディングページとして機能するケースも多々ありました。しかし近年では、「選び方ガイド」や「比較記事」など、情報量の多いブログや記事コンテンツが、検索結果上位に入るケースが目立ちます。
こうした情報系コンテンツは、ロングテールキーワードで安定した流入を獲得できるため、特集ページよりも戦略的に有利です。
3. 企画・制作リソースの圧迫やKPI未達が慢性化している場合
「とりあえず特集ページを作る」こと自体が目的化してしまっているケースも少なくありません。回遊率やCVRへの明確な貢献が見えない状態が続くようであれば、削減や統合を検討するタイミングです。
特集を「やめる or 残す」判断軸
特集ページの制作をやめるか続けるか、検討するうえでの判断軸を整理してみました。この記事をご覧になっている方のサイトではいかがでしょうか。
特集ページの見直しを検討すべきケース
| 判断軸 | 内容 |
|---|---|
| 数値面で成果が見えづらい | 特集経由CVRが低い/商品詳細ページ直流入の方が効率的な場合。 |
| 運用コストが大きい | 制作コストが高く、毎月の更新作業に多くの工数がかかっている場合。 |
| 動的ページの強化で代替可能 | レコメンド、カテゴリソート、検索強化で十分な回遊性が確保できている場合。 |
| SEO評価が得られていない | 特集が検索で評価されず、代わりにブログ記事やガイド系コンテンツが上位を獲得している場合。 |
特集ページの制作を継続すべきケース
| 判断軸 | 内容 |
|---|---|
| ブランド訴求の場として有効 | 世界観・スタイル提案でブランドの魅力を伝える場として成果がある場合。 |
| SNSやメールで使いやすい | キャンペーンやメルマガ配信時のランディング先として活用できる場合。 |
| ストーリー訴求でCVを後押しする | 高価格帯商品の購入意欲を高める導線として機能している場合。 |
| 毎月の「訪問理由」を作れる | 特集の定期更新によって再訪率がが向上している場合。 |
特集ページの効果測定に使える目的別KPI一覧
特集ページの役割に応じて、目的別にKPIを明確化するのが重要です。単にPVやCVRを見るだけでなく、「集客」「閲覧」「回遊」「リピート」といったフェーズ別に指標を整理しておくことが重要です。
以下に、目的別に確認しておきたい主要KPIをまとめました。
1. 集客施策の効果を確認したいとき
- セッション数:特集ページへの純粋な流入数(媒体別に比較)
- クリック率(CTR):バナーや広告からのリンククリック率(出稿媒体で計測)
2. ランディングページとしての質を見極めたいとき
- 直帰率:特集ページで離脱した割合(初回接触での効果確認)
- 平均滞在時間:コンテンツの読み込み状況・興味関心度を確認
- スクロール率・エンゲージメント率:ページ下部まで読まれているか(ヒートマップ)
3. サイト回遊や購入促進の貢献度を測りたいとき
- 回遊率:特集内リンクや商品詳細ページへの遷移数/全閲覧数
- 商品クリック率:特集ページ内に掲載された商品のクリック数/表示数
- CVR(購入率):特集→商品詳細→カート→購入のコンバージョン率
4. LTVやリピーター施策として活用している場合
- 再訪率:特集ページ公開後、特定期間内の再訪者数
- メルマガ開封率/CTR:特集ページがフックになっているか
現代の戦略にフィットさせるための代替アプローチ案
特集ページをやめる場合、これまで担ってきた役割をどんなコンテンツで引き継げばよいのでしょうか。その方針は、下の表のように、目的に応じて選定することをお勧めします。
| 目的 | 特集の代替コンテンツ例 |
|---|---|
| 短期キャンペーン訴求 | LP+バナーで訴求→動的ページに誘導 |
| 商品のストーリー訴求 | ブログ記事、ホワイトペーパー(例:選び方ガイド) |
| 回遊促進 | レコメンド機能+タグ分類+特定軸での動的ソート |
| リピーター向け更新 | ブランドニュース、エディトリアル系メールコンテンツ |
結論:ベストな「目的×手段」を設計しよう
現在のウェブマーケティングにおいて、特集ページは「どのサイトでも有効な手段」ではなくなっています。しかし、目的と連動させた設計ができるなら、依然として強力な武器です。
重要なのは特集ページの有無ではなく、「それぞれの目的を果たす最適なコンテンツは何か」を定義した上で、 必要なものだけを制作すること。その判断には先述のようなKPIでの検証が必須です。
検証の上で、どう着手すればよいか、数値は算出できても良し悪しの基準をどこにおくか等、悩まれる際はぜひ弊社にご相談ください。